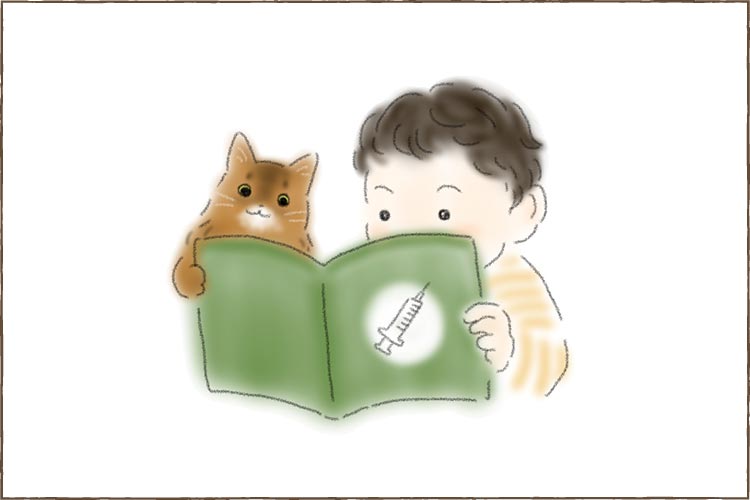乳幼児は抵抗力が未熟
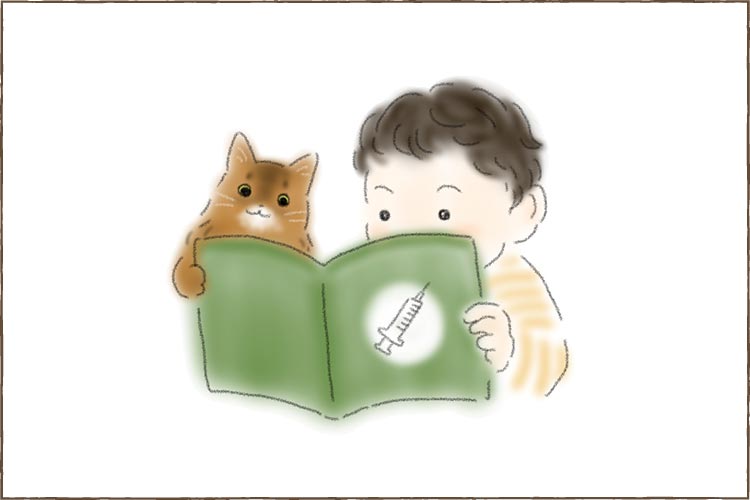
- 赤ちゃんやお子さんは病気に対する抵抗力が未熟ですし、お母さんから授かった免疫も生後数か月が経過すれば弱まってきます。これに伴い、赤ちゃんは感染症などに罹りやすくなってしまいます。病気に罹ってしまうと、重い後遺症が残ったり、生命の危険にさらされたりすることもあります。
- そうした事態を未然に防ぐために必要になってくるのが予防接種です。あらかじめウイルスや細菌に対する免疫を獲得しておくことにより、特定の病気に罹らなくなったり、仮に罹患したとしても症状が軽くて済むようになります。一般的には生後約2か月がワクチンデビューのタイミングです。
各種予防接種を行っています
- 当クリニックでは、お子さんが受けるべき様々な予防接種を行っています。事前にワクチンを用意しておきますので、WEBにて受付の上、接種をお受けください。
- なお、現在日本には数多くの予防接種があり、どのワクチンをいつ接種したらよいのか戸惑われる保護者の方も少なくないと思います。予防接種のスケジュール管理は、一般の方には少々難しいものです。そんなスケジュール管理についても、当クリニックにご相談ください。お子さん一人一人個別にワクチンスケジュールを計画いたします。
お持ちいただくもの
- 予防接種の際にお持ちいただくものは、原則として予防接種予診票、母子健康手帳、健康保険証、小児医療証、診察券(お持ちの方)です。
- 万一の副反応に備えて、接種後30分程度は接種場所の近くに留まっていましょう。接種当日はいつも通りの生活をして構いませんが、激しい運動は避けてください。接種後、体調の変化が見られた際は、すぐに医師にご相談ください。
定期接種と任意接種
- お子さんが受ける予防接種には、法律に基づいて地方自治体(市町村など)が実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。このうち定期接種は、集団予防を目的とする感染症(A類疾病)と、個人予防を目的とする感染症(B類疾病)に分類できますが、小児期に受ける接種はA類疾病を予防するために行われます。
- 任意接種は、保護者の方のご判断で受けるか否かを決めるものであり、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)やインフルエンザなどを予防する目的で行われます。
- なお、どちらのタイプであっても、接種予定日に発熱などの体調不良が見られた場合は、その日のワクチン接種は延期し、体調が良くなってから接種することになります。どのくらい延期するのかは症状によって異なりますので、お子さんの体調が優れないときは速やかにご相談ください。
筋肉内接種と皮下接種
- 15価の肺炎球菌ワクチンや5種混合ワクチンは、その他のワクチンと同様の皮下注射による接種以外に、筋肉内注射による接種が可能です。筋肉内接種は、皮下接種に比べて痛み、発赤、発熱などの局所反応が少なく、免疫を獲得する程度は同等かそれ以上であるため、当クリニックでは筋肉内接種をお勧めしています。
定期接種の種類
ヒブワクチン(不活化ワクチン)
- ヒブ感染症(インフルエンザ菌b型による感染症)を予防するためのワクチンです。2024年4月以降は5種混合ワクチンが原則になりましたが、すでにヒブワクチンの接種を始めている場合には、従来どおりヒブワクチンを続けます。
- 標準的な接種期間は、生後2か月~5歳未満。接種回数は1~4回です(接種開始年齢によって異なります)。
小児肺炎球菌ワクチン(不活化ワクチン)
- 肺炎球菌による感染症を予防するものであり、細菌性髄膜炎や菌血症、敗血症、重い肺炎、細菌性中耳炎などのリスクを軽減できます。2024年4月以降はこれまでの13価から15価へ変更となり、より多くの感染症を予防できるようになりました。これまでどおりの皮下接種に加えて筋肉内接種が可能です。
- 標準的な接種期間は、生後2か月~9歳。接種回数は1~4回です(接種開始年齢によって異なります)。
B型肝炎ワクチン(不活化ワクチン)
- B型肝炎ウイルスによる肝炎や肝硬変、肝がんのリスクを予防するワクチンです。
- 標準的な接種期間は、生後2か月から。接種回数は3回です。
5種混合ワクチン(不活化ワクチン)
- ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ感染症を予防するワクチンで、筋肉内接種が可能です。
- 標準的な接種期間は、生後2か月~7歳6か月未満。接種回数は4回です。
4種混合ワクチン(不活化ワクチン)
- ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオを予防するワクチンです。2024年4月以降は5種混合ワクチンが原則になりましたが、すでに4種混合ワクチンの接種を始めている場合には、従来どおり4種混合ワクチンを続けます。
- 標準的な接種期間は、生後2か月~7歳6か月未満。接種回数は4回です。
2種混合ワクチン(不活化ワクチン)
- ジフテリアと破傷風を予防するワクチンです。
- 標準的な接種年齢は11歳~12歳未満。接種回数は1回です。
水痘ワクチン(生ワクチン)
- 水痘(水ぼうそう)を予防するワクチンです。従来は小児を中心に非常に多くの罹患者がいましたが、2014年10月から定期接種となったため、今後は水痘の発症者が減少すると期待されています。
- 標準的な接種期間は1歳以上であり、接種回数は2回です。
BCGワクチン(生ワクチン)
- 結核を予防するワクチンです。ヒトに対する毒性が失われて抗原性だけが残った結核菌(BCG)を接種することにより、乳幼児結核を予防することが出来ます。
- 標準的な接種期間は、生後5か月~8か月未満。接種回数は1回です。
麻疹・風疹混合ワクチン(生ワクチン)
- 麻疹(はしか)と風疹を予防するワクチンです。
- 標準的には、まず1歳のときに1回、さらに小学校の入学の前年に1回です。
日本脳炎ワクチン(不活化ワクチン)
- 日本脳炎を予防するワクチンです。
- 標準的には、まず3歳~4歳の間に合計2回、その2回目接種から1年後にもう1回。さらに、9歳~10歳までの期間に1回です。
ロタリックス(生ワクチン)
- ロタウイルスによる胃腸炎を予防するためのワクチンです。臨床効果はロタテックと概ね同じです(製薬メーカーが異なります)。
- 標準的な接種期間は、生後6週~24週。接種回数は2回です。
- 接種前後30分は授乳が出来ませんので、ご注意ください。
ロタテック(生ワクチン)
- ロタウイルスによる胃腸炎を予防するためのワクチンです。臨床効果はロタリックスと概ね同じです(製薬メーカーが異なります)。
- 標準的な接種期間は、生後6週~32週。接種回数は3回です。
- 接種前後30分は授乳が出来ませんので、ご注意ください。
子宮頸がんワクチン(不活化ワクチン)
- 子宮頸部に出来るがんを予防するワクチンです。
- 小学校6年生から公費で接種可能です。接種回数は接種開始年齢や接種間隔によって異なり、2回から3回です。
任意接種
おたふくかぜワクチン(生ワクチン)
- おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)を予防するワクチンです。
- 標準的な接種期間は、1歳から。接種回数は、現行では2回とされています。
A型肝炎ワクチン(不活化ワクチン)
- A型肝炎ウイルスによる肝炎を予防するワクチンです。
- 標準的な接種期間は、生後1歳から。接種回数は3回です。
インフルエンザワクチン(不活化ワクチン)
- インフルエンザを予防するワクチンです。
- 長期間にわたって強い感染防御免疫が誘導されるポリオワクチンなどとは異なり、ウイルス感染やインフルエンザの発症を完全に防ぐことは出来ません。しかし、インフルエンザに罹患した場合に、重篤な合併症を防いだり、症状の悪化を抑える効果が期待できます。
- 生後6か月~12歳までは2回の接種、13歳以降は1回の接種が推奨されています。
経鼻インフルエンザワクチン(生ワクチン)
- 鼻孔に噴霧するタイプの「痛くない」ワクチンで、インフルエンザを予防します。
- その効果は不活化ワクチン(注射)と同程度ですが、1回の接種で効果が約1年間持続します。
- 2歳~18歳が対象(当院では、中学生まで)です。
- 鼻孔に噴霧するため、泣いてしまう児や、鼻汁の多い児は効果が落ちる可能性があります。
- 接種後1週間くらいまで鼻汁・咳嗽・咽頭痛などの軽い感冒症状が出ることがあります。
- 他のワクチン(生ワクチン、不活化ワクチン)との接種間隔に制限はありません。
接種できない方
- 対象年齢に入っていない
- 37.5℃以上の発熱がある
- 喘息発作がある
- 免疫不全者:免疫抑制剤の使用、ステロイドの長期使用、無脾症、白血病など
- ミトコンドリア脳筋症患者
- ゼラチンアレルギー
- 中枢神経系の解剖学的バリアー破綻がある:人工内耳埋め込み、頭蓋顔面奇形など
- 妊婦
接種に注意が必要な方
- 喘息の既往がある
- アスピリンの内服をしている
- 抗インフルエンザ薬を内服して間もない
48時間以内 :オセルタミビル(タミフル)、ザナミビル(リレンザ)
5日以内 :ラニナミビル(イナビル)、ペラミビル(ラピアクタ)
17日以内 :バロキサビル(ゾフルーザ)
- 授乳婦
- 周囲に免疫不全者がいる
- 診療科目
- 小児科、アレルギー科
- 住所
- 〒277-0945 千葉県柏市しいの木台5丁目25-7
- アクセス
- 東武野田線 高柳駅、新京成線 五香駅
- 駐車場
- 駐車場16台分有
※混雑状況によっては、早めに受付を終了することがあります
休診日:土曜午後、水曜・日曜・祝日
●乳幼児健診、予防接種(時間予約制)
| 診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日祝 |
| 9:00-12:00 |
● |
● |
/ |
● |
● |
● |
/ |
| 14:00-15:00 |
● |
● |
/ |
● |
● |
/ |
/ |
| 15:00-18:00 |
● |
● |
/ |
● |
● |
/ |
/ |